※この記事にはプロモーションが含まれます
「気づけば推しに何十万もつぎ込んでいた」
「冷静になると、なぜここまでお金を使ってしまったのか自分でもわからない」
そんな経験、ありませんか?
推しにお金をかけることは、決して悪ではありません。
むしろ、経済を回し、自分の気持ちに正直に行動している証です。
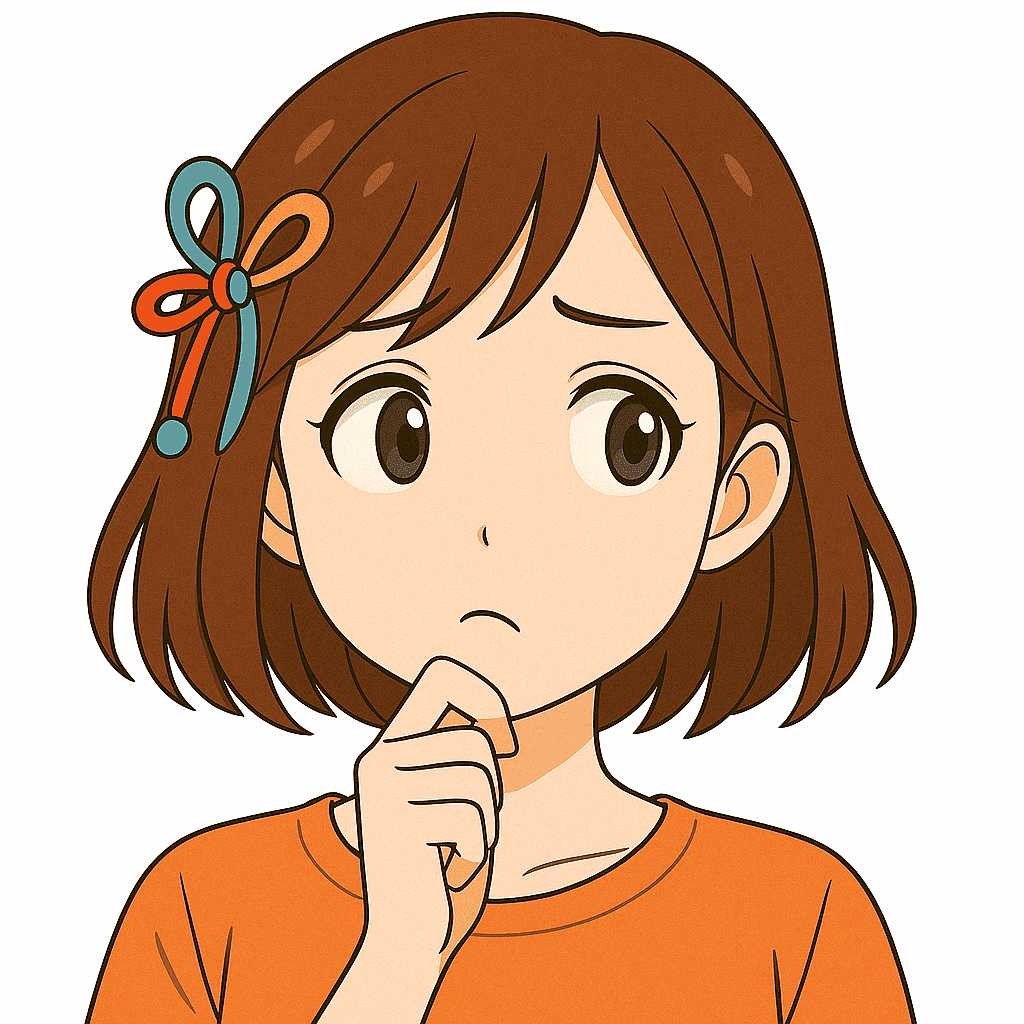
でも、もしそこに「自分のことをないがしろにしていたかもしれない」という違和感があるなら…
この記事では、推し活にお金をつぎ込む心理の背景と、そこから抜け出すヒントを心理学と経済的視点の両面から考察していきます。
なぜ私は、推しにここまでお金を使うのか?
推し活でお金を使うことに、強い快感や満足感を感じる人は少なくありません。
- 応援したい!という純粋な気持ち
- 推しグッズを持つことで得られる安心感
- SNSに載せて“推しに貢いでる私”を共有したい気持ち
こうした行動の根底には、「自己承認欲求」や「自己効力感(self-efficacy)」が関係しています。
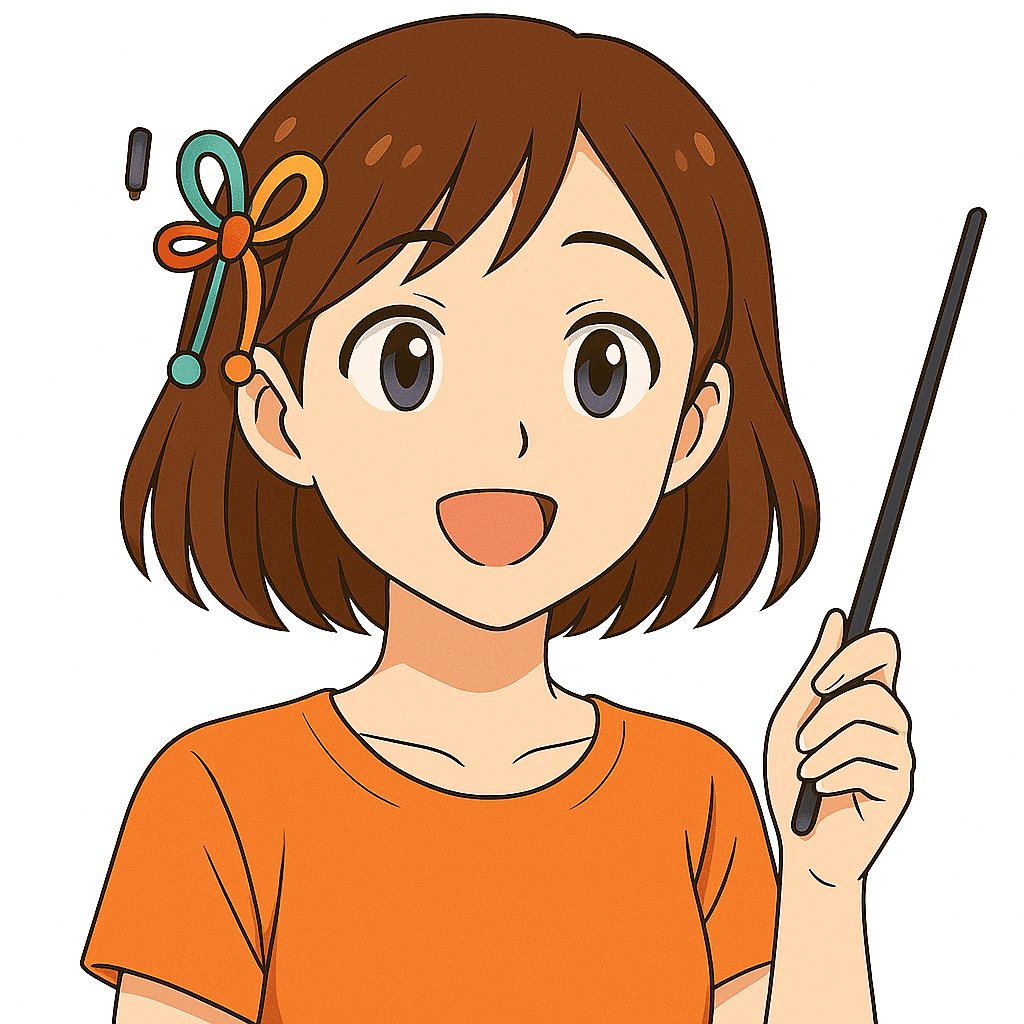
自己効力感ってなに?
「自分ならこれができる!」って信じる力のこと。
推しにお金を使うことで、「私は推しの力になれてる」と感じるのも、自己効力感が関係しているよ。
お金を使うことで、自分が“推しに貢献している存在”になれているという実感。
それが自分の存在価値を強く補強してくれているのです。
育った環境と、親のお金の価値観も影響している
実は、「推しにお金を使いすぎる傾向」には、幼少期の家庭環境が関係していることもあります。
- 親が節約志向だった → 子ども時代にお金を自由に使えなかったため、大人になって“解放”のように使ってしまう
- 親が浪費家だった → お金を使うことにブレーキが効きづらい
- 「頑張ったごほうび=モノやお金」だった → 成果と消費がセットになる思考パターンが染み付いている
これは、行動経済学やスキーマ理論で説明される“お金との付き合い方の刷り込み”です。
子どもの頃の記憶や感情は、大人になってからの購買行動に無意識に影響を与えています。
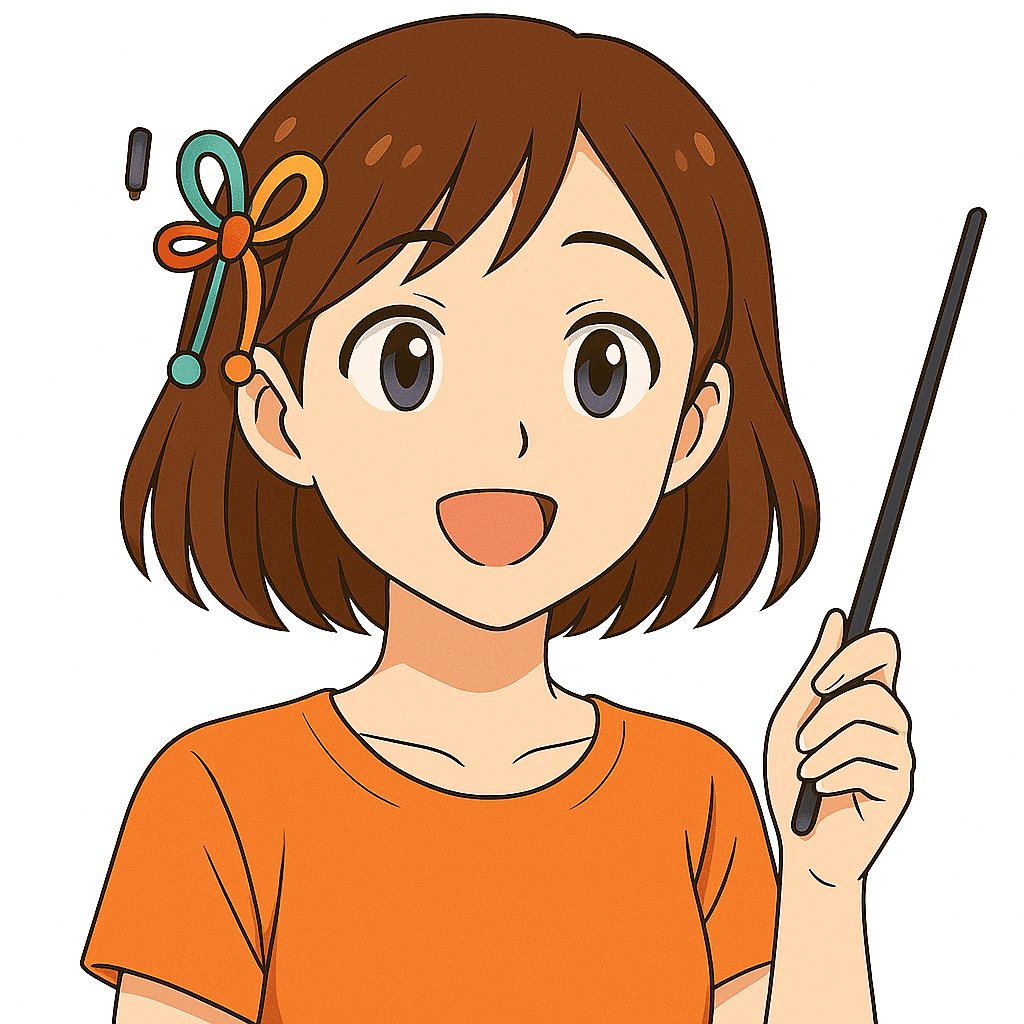
スキーマ理論って?
子どもの頃の経験や価値観が、大人になってからの「当たり前の行動パターン」になるという心理学の考え方。これが無意識のうちに現在の推し課金行動に影響していることも。
「推しに使ってる私」が目的になっていない?
気をつけたいのは、いつの間にか“推しを応援する”ことではなく、「推しに貢いでる自分」「課金してる私」が目的になってしまっているケースです。
▼他人より多く買ったことで満たされる
▼グッズの数や金額で愛情を証明したくなる
▼SNSで推し愛アピールをするための課金
このような状態では、推しへの愛よりも“承認されたい自分”が前に出てしまい、どれだけお金を使っても満たされないというスパイラルに陥ることもあります。
「そっか、だから私は…」と気づくことが第一歩
推しにお金を使う自分を責める必要はありません。
でも、「なぜそうしていたのか?」を言語化して理解できると、行動が少しずつ変わっていきます。
「推しを応援してるつもりが、推しに貢いでる私に酔ってたかもしれない」
そんな気づきが持てたら、それはとても健全なサインです。
自分のためのお金の流れ(キャッシュフロー)も大切に
推し活は人生の彩りです。
でも、推しだけにお金が流れていて、自分への投資がゼロという状態は、いずれ息切れしてしまいます。
- 推し活の予算を月ごとに設定する
- 推し活とは別に「未来の自分」への積立も始める
この「お金の2軸管理」が、心にもお財布にもゆとりを生み出します。
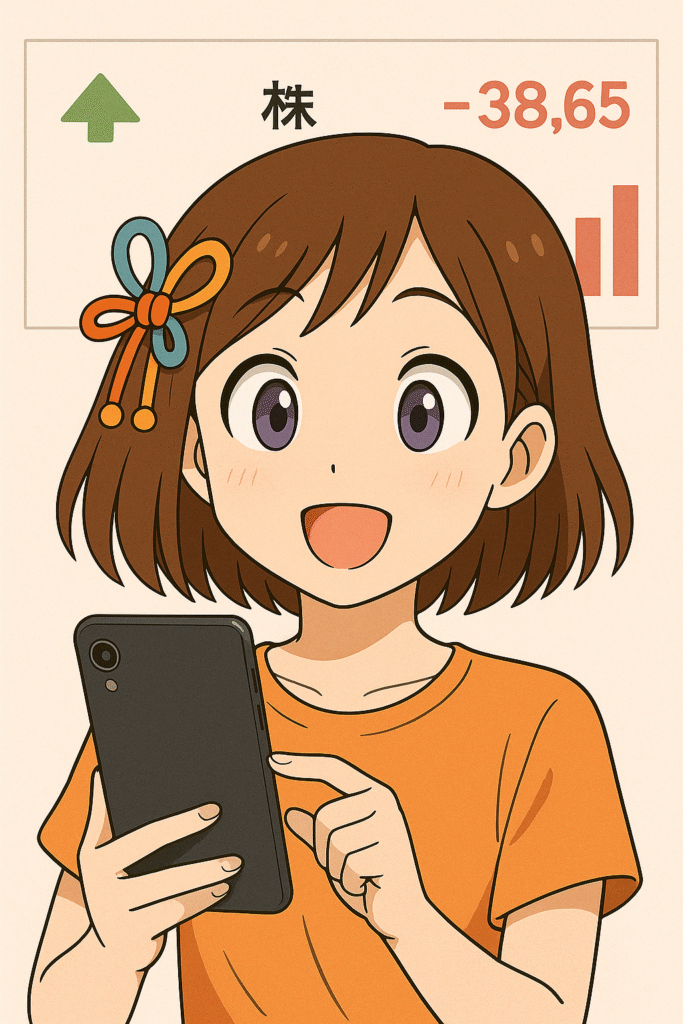

推し活も大事。そのための揺るぎない土台作りはもっと大事!
資産形成=自分の推し活を長く続けるための準備
毎月の余剰資金を、ただ貯めておくだけではもったいない。
投資信託などで資産を育てておくことで、未来の推し活資金を自然に作っていくことができます。
証券口座の開設は思っているよりもずっと簡単で、たとえば以下のような証券会社が初心者におすすめです。
◾ DMM証券
- スマホだけで口座開設が完結
- 最低100円からの積み立てが可能
- 画面がシンプルで、初心者にもわかりやすい
◾ SBI証券
- 楽天と並ぶ大手で信頼性が高い
- つみたてNISAやiDeCoにも対応
- 手数料が安く、長期運用向き
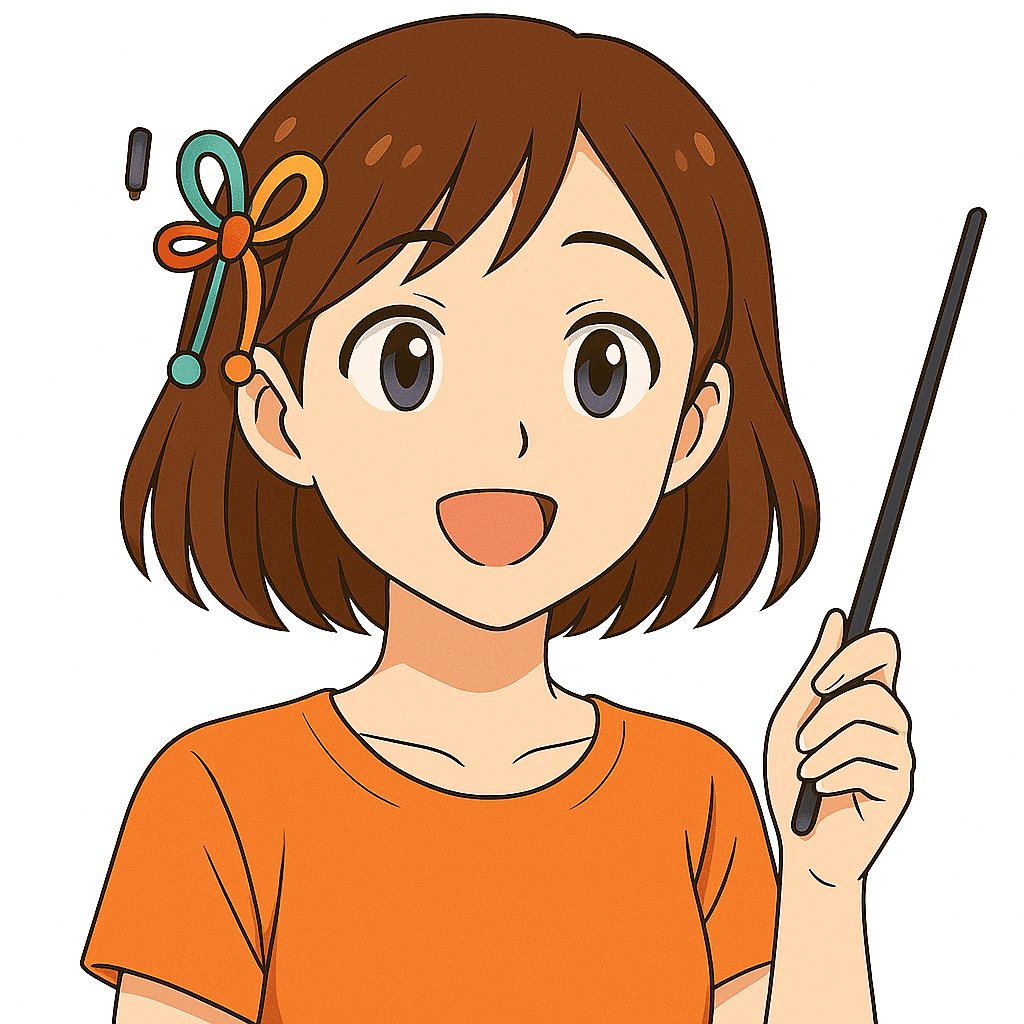
毎月決めた額を自動的に積立投資に回すことで、貯める習慣が身についていきます。
まとめ:推しも大事、自分も大事。
「推しのためにお金を使う」ことと、「自分の未来のためにお金を育てる」こと。
この2つはどちらかを選ぶものではなく、両立できるものです。
今の自分を喜ばせながら、未来の自分にもありがとうと言われる。
そんなお金の使い方ができたら、推し活はもっと自由で楽しくなるはずです。
※投資は元本保証ではありません。無理のない範囲で、ご自身のライフスタイルに合った方法を選びましょう。信頼できる書籍やサービスで知識を深めながら、自分のペースで資産形成を始めてみてください。


コメント